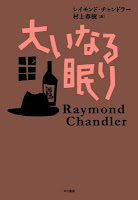2012-12-31
アガサ・クリスティー「もの言えぬ証人」
多くの財産をもつ老婦人エミリーとそれにたかろうとする浪費家の姪や甥たち。やがて身の危険を感じる出来事が起こり、エミリーはエルキュール・ポアロに手紙をしたためる。だが、実際にポアロの元に届いたそれは、書かれてから二ヶ月後に投函されたものであった。事件の可能性を見て取ったポアロはヘイスティングズとともに夫人の住む屋敷に向かった。しかし、彼女は既に亡くなっており、その財産の殆どは親族ではなく身の周りの面倒を見ていた家政婦に残されていたのであった。
文庫本で500ページほどあって、いままで読んだクリスティ作品のなかで一番長いお話かな。タイトル『もの言えぬ証人(Dumb Witness)』は被害者の飼っていた犬を指しているようで、本書の献辞もクリスティの愛犬ピーターに捧げられています。
そもそも犯罪があったのかさえはっきりしない状況が扱われていて、なかなか推理の取っ掛かりがない。気が付けば300ページくらいまで読み進めているのに、未だ雲をつかむような話のままなのだ。それでも、ちょっとしたフックで興味を繋いでいき読者を退屈させない手際は、いつもながらに大したものである。
また、ヘイスティングズの存在による牧歌的な雰囲気が特に強く感じられるのだけれど、彼はこの作品を最後にお役御免となって、その復帰はシリーズ最終作『カーテン』まで無いようですね。
大詰めにおける推理は物証が無いゆえに性格分析に大きく頼るもの。関係者の不可解な行動を心理から解き明かす部分はなるほど、さすがと唸らされるものでありますが、その反面、犯人絞込みの説得力は乏しい。ただフーダニットとしての興味とは別に、女史の作品では珍しい趣向があって、これが面白い。
犯人当ての興趣には欠けますが、非常に独創的な構図を持つ物語であります。結局、公的には何の事件も起こっていないのだし、殺人が行なわれたことすら証明するものはポアロの言葉以外に無いのだから(それが意図的なものであるのは、小説内に警察官が一度も登場しないことからも明らかでしょう)。
2012-12-30
Satisfaction Unlimited / Think Of The Children
サティスファクション・アンリミテッドというボーカルグループがホランド=ドジャー=ホランドのホット・ワックスから1972年にリリースした唯一のアルバム。
ノーザンといえばそうなのだが、ホット・ワックス/インヴィクタスと聞いて考えるようなものとはまるっきり違う音であります。結構、例えようがない個性というか。あえて言うなら'60年代のテンプテーションズがニューソウルを演っている、という感じ。
メンバーには'50年代の終わりから活動しているひともいるようで、ドゥーワップを根っこに持つような端整なコーラスに、良い声で温かみのあるリードで、オーソドックスながらバランスが凄くいいです。
曲のほうはミディアムが殆どだけれど、ダンサーよりもメロウさが際立つ仕上がりのものが多い。といっても甘すぎず、しなやかで包み込むようであって、気持ちよくグルーヴに浸っていられる。これもまたソウルミュージックの魅力であるよね。
強烈な持ち味は無いようでいて、実は似ているものが他に見当たらない音楽では。
非ソウルファンにも聴いてもらいたい一枚です。
2012-12-25
ジョン・ディクスン・カー「曲がった蝶番」
若い頃、アメリカに渡る際に沈没したタイタニック号に乗り合わせた過去のあるファーンリー家の次男ジョンは、今ではケント州にある屋敷の当主に落ち着いていた。だが、我こそは本物のジョン・ファーンリーだと主張し、その証拠もあるという男が現れる。弁護士立会いの下、二人のジョンがまさに決着を付けんとするときに怪事件が。
ここ最近、創元が力を入れているカー新訳、1938年だからこれも作者に脂の乗っていた時期の作品ですね。旧『曲った蝶番』は大昔に読んでいるのですが、記憶はあいまい。上に書いたような設定はなんとなく覚えていたけれど。
ミステリとしては衆人環視下の犯罪、いわゆる準密室なのですが、それに加えてどちらのジョンが本物なのか、事件は自殺なのかそれとも他殺なのか、という問題も絡んでなかなかに広がりのあるものになっています。更に悪魔崇拝の儀式や不気味な自動人形による怪奇趣味も充分。
また、プロットもミステリのルーティンを意識しつつ、そこからずらした展開が愉しいし、途中で披露される仮説も手が込んでいてと、とにかく読者を飽きさせないサービスが満載です。
さて、真相なのですが。
終章で明らかにされる強烈なトリックは推理困難なものであり、その異様なテイストは乱歩が好みそう。ただ、全体に色々と手を広げ過ぎたせいか、解決全体として見るとごたごたしている感は否めないところ。細かいひとなら証言の扱いがアンフェアだと思うのでは。
カーの個性が非常に強く出た一作であって、好みは分かれそうですな。完成度は置いといて、個人的には無類に面白かったのですが。
2012-12-24
Gil Scott-Heron / The Revolution Begins
どうしようもなくなって落ち込んだときには
ビリー・ホリディやコルトレーンを聴けばいい
彼らが問題を洗い流してくれるさ
("Lady Day And John Coltrane")
英Aceからギル・スコット・ヘロンのキャリア最初期、フライング・ダッチマン・レーベル在籍時に残した録音を纏めた三枚組CDが出ました。
ギルはこの当時三枚のアルバムを制作しているのだけれど、今回のセットではそれらのシークエンスがばらされているので、そこは好みが分かれるところ。
ブックレットには当時のスタジオ風景の写真が多く載せられ、ライナーノーツは相棒ブライアン・ジャクソンやプロデューサーのボブ・シールのコメントが盛り込まれたもので読み応えがあります。
ディスク1は「SONGS」と題されていて、唄物を集めたもの。ファースト「Small Talk At 125th And Lenox」(1970年)から2曲、セカンド「Pieces Of A Man」(1971年)からは1曲を除いた全部、サード「Free Will」(1972年)から半分。改めて聴いても、都会的で硬派な面とメロウさのバランスが実に格好いい。
今まで敬遠して聴いていなかったファーストにも唄物といっておかしくないトラックがあった、と判ったのが個人的には収穫。しかし、せめて制作時期順に曲を並べて欲しかったというのが本当のところです。
ディスク2は「POETRY, JAZZ & THE BLUES」。内容は三枚のアルバム収録曲のうちディスク1に入れてない曲全て。殆どがポエトリー・リーディングで、箸休めのようにブルースがちょこちょこ混じっています。バックがパーカッションのみのものが多く、内容は社会的テーマが中心で口調も堅めとあって、CD1枚通して聴くのはなかなかキツイものがある。
バーナード・パーディのアルバムに客演したときの曲もひとつ入っているのだけれど、これといって特徴のないブルース。このディスクはあんまり聴かないかも。
ディスク3「THE ALTERNATE FREE WILL」はその名の通り、サードアルバム「Free Will」のオルタネイト集で、「All previously unreleased」と書かれています。ただ、僕は未聴なのだけれど過去に「Free Will」に8曲の別テイクを付けたCDが出ていたそうなので、もしかしたらそれとダブるものもあるかもしれません。
リマスターは文句無し、ナチュラルで長時間聴いていても疲れない。いつもながらAceの仕事は抜かりが無い。
ただし、入門編には向いていないセットではあります。これから初期のギル・スコット・ヘロンを聴こうか、というひとにはやはり単体で「Pieces Of A Man」を勧めます。
2012-12-23
法月綸太郎「犯罪ホロスコープⅡ 三人の女神の問題」
法月版「犯罪カレンダー」、その後編。
収録されている六短編のうち、前半三作にはストレートなフーダニットが並んでいます。キャラクターの扱いが実に淡々としていて、容疑者が伝聞でしか登場しない作品もある。そしてその分、謎解きは濃ゆいものになっています。
「宿命の交わる城で」 次々に意外な仮説が提示される様が作者の初期作品を思わせるようで、とても密度の高い短編。ねじれた犯罪の構図は勿論、小説としての人を食った趣向も洒落てる。
「三人の女神の問題」 非常にパズル的な要素が強い一編。これも錯綜した事件のもつ奥行きが素晴らしい。構図の反転も鮮やかに決まったし、ねちっこい推理も良い。
「オーキュロエの死」 シンプルな構成要素にして複雑なプロットが凄い。星座を絡めた趣向もばっちり決まった。
後半の三作は設定そのものがちょっと変わったものになっています。そもそもメインとなる謎が何なのか、というところから捻っていて。
「錯乱のシランクス」 被害者自身が後から書き足したダイイング・メッセージという妙。これはいかにも後期クイーンらしいな。
「ガニュメデスの骸」 奇妙な誘拐事件は意表をついた展開を見せていく。その先読みさせないプロットが見所。
「引き裂かれ双魚」 異様な論理を扱ったものであるが、ダイイング・メッセージの補助的な使い方が面白い。意図せぬところに暗合を見てしまうところなんか丁寧。
ロジック/プロットいずれに重心をかけた作品であっても、ちゃんと意外性があるところが良いですな。星座の縛りを守りながらバラエティもあって、オーソドックスな探偵小説好きを満足させてくれる短編集です。
2012-12-22
Del Shannon / Home & Away
デル・シャノンの英国レコーディング音源、制作は1967年。プロデューサーとしてはアンドルー・ルーグ・オールダムがクレジットされており、アレンジはアーサー・グリーンスレイド、演奏にはスタジオミュージシャンに加え、イミディエイト・レーベルの人脈が多く参加しているようです。
内容はアンドルーの趣味のウォール・オブ・サウンドに、フォークロックとバロックポップの混交、といった感じ。しかし、英国のスタジオで英国のミュージャンによって作られた音であるにも拘わらず、デル・シャノンのボーカルが乗っかるとアメリカンポップに聞こえる不思議。どういうことだろう? と考えながら何度も繰り返し聴いてしまった。シンガーとしての格なのか、湿り気のない明快な唄声がバックのいかにも英国らしい陰りを帯びたトラックを支配しているよう。
曲によってはサウンドと唄にミスマッチな感を覚えるものもあるのだけれど、結果的にはそのことによってちょっとした掴みどころの無さと独特の奥行きが出ているようでもある。
楽曲はビリー・ニコルズやトゥワイス・アズ・マッチらによるものと、デル・シャノン本人が書いたものが混在しているのだけれど、メランコリックな佳曲が多いですね。
唯一、これは浮いているんじゃないかと思ったのが "Runaway '67"。かつてのヒット曲をテンポを落としゴージャスなオケを使って再演したもので、アンドルーのスペクター・コンプレックスが悪いほうに出たかな。
当時のイミディエイトの音が好きな人なら、聴いて損はない一枚ではないかと。
2012-12-16
レイモンド・チャンドラー「大いなる眠り」
二年ぶりとなる村上春樹訳チャンドラー、その第四弾。我が国では双葉十三郎が訳した東京創元社版で長らく親しまれてきた作品だけれど、この本も「翻訳権独占 早川書房」と腰巻には書かれていて、どうもチャンドラーの作品の版権はすべて早川に移行したようであるね。数年前にこの作品は田口俊樹が訳し直した、それが創元から新たに出る、という話があったそうなのだけれど。
『大いなる眠り』は長編第一作だ。スタイルは既に完成されているのだけれど、後年のものと比較するとフィリップ・マーロウは若々しい。やたらと感傷にひたることもないし、比喩もぶっきらぼうだ。脇筋も控えめ、引き締まった文章はこの作品ならではであって、チャンドラー長編の中では一番ハードボイルド小説らしい。
筋を説明する必要があるだろうか? 特に珍しいところはない、金持ちの依頼人が身内の持ち込んだトラブルに片を付けるために探偵を雇う、いつもそんなお話だ。
チャンドラーが偉大な先達・ハメットから受け継いだことのひとつは、読者に先読みさせない展開だろう。いや実際、なぜこんな風に話が繋がるのだろう、と不思議に思う。
そして、マーロウが情報を売り込まれた後に考える、こんなくだりがある。
「話はいささか整いすぎていた。そこに見受けられるのは複雑に織り込まれた事実の模様ではなく、そぎ落とされたフィクションの単純さだった」
あるいは、その一見した脈絡の無さと、偶然もしくは運命的なタイミングに支配された展開こそが彼にとっての現実らしさなのだろうか。
この作品は十年以上読み返していなかったのだけれど、マーロウが依頼人と温室内で会う場面は良く覚えていたな。
2012-12-09
デュレンマット「失脚/巫女の死」
スイスの劇作家、フリードリヒ・デュレンマットの中短編集。採られている作品はいずれもエンターテイメントとして読めるものばかりであります。300ページちょっとで千円越え、と文庫本にしてはちと値が張るのだけれど。
「トンネル」はオーソドックスな不条理ものですが、まあ、でぶのドタバタ劇です。心理に深く踏み込まず、淡々とした描写によって生み出されるそこはかとないユーモアもいい。軽々しく「ここではないどこか」とか言ってるやつらは皆、この列車に乗ればいいのだ。
「失脚」で描かれているのは独裁政治のグロテスクなカリカチュア。革命をめぐる奇妙な論理が展開するうちに、状況が一転していく。恐怖に支配された喜劇でもあって、笑いながら読みました。
「故障」はミステリの世界でもありそうな設定のものであるけれど、展開が読めるよな、と思っているとあれあれ・・・。チェスタトン的でもあるか。
最後の「巫女の死」は有名なギリシア悲劇を素材にして好き放題遊び倒した一編。死に瀕した巫女の前に「オイディプス王」の登場人物たちの幻が次々にあらわれ、真相は実はこうだったのだ、とそれぞれに違う告白をしていく。繰り返しギャグでもあるし、ミステリのパロディとしても読めるか。
少し理屈っぽいですが、初期の筒井康隆みたいなところもあって気に入りました。結末において物語世界の底が抜けるような感じで、寓意を探ろうとすればいくらでも掘れそうではありますが、まずはただただ面白く読むが吉かと。
2012-12-02
Tami Lynn / Love Is Here And Now You're Gone
タミー・リンというニューオーリンズ出身の女性シンガー、1965年にバート・バーンズ制作で "I'm Gonna Run Away From You" をリリースしていますが当時は話題にならず、その後はセッションシンガーとして活動していたそう。1971年にはジェリー・ウェクスラーから声が掛かり、マイアミのクライテリアスタジオにおいてウェクスラー&ブラッド・シャピロの元でシングルを制作したものの、これもヒットには結びつかなかった。しかし同年、イギリスの所謂ノーザンソウルシーンで前述の "I'm Gonna Run Away From You" に火が付いたそうで。そのイギリスでのリイシューを企画したジョン・アビイというひとが、タミーをマラコスタジオに連れて行って作られたのが、「Love Is Here And Now You're Gone」(1972年)というアルバムです。
アナログA面にあたる前半はメドレーというか組曲風で。収録されている4曲は全てカバーなのだけれど、その間を語りが繋ぐことでひとつのストーリーが構成されているという具合。
頭から3曲は控えめな演奏による、カントリーを隠し味にしたようなしっとりしたスロウなのですが、丁寧で表情の細やかなボーカルがしっかりと嵌っています。中では、タイトルにもなっているスプリームスのヒット曲がメロディはそのままにぐっとテンポを落としたものになっていて。淡々とした演奏を背景にすることで、展開をはらんだメロディが一段と際立っているようで、気に入りました。
そして、スロウがずっと続いた最後にはキャッチーなミディアム "That's Understanding" が来るのだけど、これがそれまでの抑えに抑えた流れからの開放感もあって、ばっちり決まった。
対して、アルバム後半はポップで軽快なダンサーが中心になっていて、あっさりした唄い口は曲調に合っていると言えばそうなんだけど、ソウルのプロパーなファンにはもの足りなく感じられるかも。
ただ、最後にはマイアミ制作のシングル両面が続いていて、それらはタイトで都会的なテイストのサウンド。呼応するようにボーカルも力強く、これには満足。
軽量級ではあるけれど、南部らしい甘さを滲ませた佳品だと思います。やはりロマンティックな前半がしっかりと作られていて良いな。
2012-11-26
Roger Nichols And The Small Circle Of Friends / My Heart Is Home
ロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ、5年ぶりとなる3枚目のアルバムがリリースされました。
前作「Full Circle」のジャケットは彼らの若い頃の写真があしらわれ、春を思わせるようなデザインでしたが、今回のものに写っているのは現在の姿であり、秋あたりを感じさせる色合いになっています。
そして、内容からもそれに呼応するような変化を感じます。「Full Circle」からは昔のイメージを手堅く守るような意図が見えたのに対し、今作はそういったものにとらわれず、レゲエっぽいアレンジやジャズコーラス風の曲まであって、コンテンポラリーな自由度が高くなっています。シンセの使い方も前作ではいかにも低予算ゆえ管弦の代用品という感じだったのが、今作ではもっと思い切って鳴らしていて、うまく嵌った場合にはコーギスにも通じるようなテイストが生まれているのが面白い。
ただ、そういったいろいろな試みをやってはいても奇を衒ったような感じがしない節度はいいですね。むしろ、アルバム全体としては前よりもぐっと落ち着いたものになったという印象を受けました。
勿論、芯となるうたは彼らならではの魅力を湛えたものなのです。これがあるからこそ変化することが可能だったのでしょう。
有名曲としては "We've Only Just Begun" が何と言っても目を引きます。親密な感じも好ましい仕上がりで。うんうん、改めて聴いても良い曲だわ。あと、ロジャー最初期の作品だという "Something From Paradise" は'60年代的なフックが効いていて楽しいですな。
書き下ろしの新曲も押し付けがましいところやわざとらしさのない、クラシックで美しいポップソングばかりで。いつものロジャニコ節が堪能できますよ。
若いリスナーにアピールするような要素は減退しました。もはや「ソフトロック」という呼称も似つかわしくないですが、これが現在の彼らを表わした音楽ということなのかも。
アーティストとともに歳を取ることを受け入れていこうか、そんな気にさせられる一枚です。
2012-11-25
R・A・ラファティ「昔には帰れない」
「”わたしがちょっと家をあけると、いつもこうなんだから”――どこかの母親が、食われたばかりの子供の下顎骨と頭頂骨を手にとって、そういったそうな」
当初の予定より少し遅れましたが、ちゃんと出ましたラファティの日本オリジナル短編集。
2部構成になっており、第1部には比較的シンプルな作品が集められています。書き出しにおいてアイディアがはっきりと提示されているし、ねじれた物語もまるでアメリカの田舎に昔から伝わる大らかなホラ話のように砕いて語られていて。エンターテイメントとしてよく出来ているものばかり。
なかでも気に入ったものをば。
「素顔のユリーマ」 頭からケツまで逆説に貫かれたような物語。子供のまま歳を取ってしまったような主人公は作者の自画像でもあるのだろうか。
「月の裏側」 何ということの無い日常の事件、それをSFとして語ってしまうセンス・オブ・ワンダー。
「ぴかぴかコインの湧きでる泉」 繰り返しの展開の末にくる宙ぶらりんの結末が巧みすぎ。
「昔には帰れない」 地上に浮かぶ小さな月、のイメージだけで既にとても魅力的なのだが、そこに子供時代へのノスタルジーも絡まって、いや楽しい。
そして第2部。こちらは変な作品が多い。陽気でペシミスティック、そしてわけわからんがぐいぐい読まされる。これぞ比類なきラファティ。
こっちで印象的だったのは。
「忘れた偽足」 異星人の生態に異星人のユーモア。理解を越えるエピソードが次々と繰り出されるけど、どこか論理的な筋道も感じられる。そして終末のみに許されるハッピーエンドが良い。
「大河の千の岸辺」 分割され、圧縮・梱包された古代の岸辺そのもの、というイメージが素晴らしい。
「行間からはみだすものを読め」 すさまじい饒舌とあまりに不自然な設定に、もはや何が起こってもおかしくはないという気にさせられる。現実の崩れ方もまた、いとをかし。
「一八七三年のテレビドラマ」 偽の歴史を背景にした額縁小説。表の物語を裏側が侵食してしまう趣向はSFとしても胡散臭すぎるのだが、その出鱈目さがかえって楽しい。
退屈なものがひとつとしてない、純粋にSFを読む愉しみが詰まった短編集でありましたよ。
2012-11-24
Daughters of Albion / Daughters of Albion (eponymous title)
リオン・ラッセルがプロデュースを手がけた、西海岸の男女デュオによる唯一のアルバムで、リリースは1968年。英Now Soundsからのリイシューなんだけれど、正規のCD化としては初、と書かれていまして。以前、Falloutというところからも出ていましたが、そちらはブートということなんでしょうか。
ウィリアム・ブレイクの作品から取ったというグループ名やアングラ臭漂うジャケットに反して、内容はサイケデリックな味付けも華やかな、しっかりしたプロダクションのポップスです。
デュオのうち、女性ボーカルのキャシー・イエッセは癖がなくて伸びやかな美声で、ジェントル・ソウル期のパメラ・ポランドを思わせるところがあります。
一方で作曲をしている男性、グレッグ・デンプシーの方は唄はそんなに良くないのだけど、そもそもはスクリーン・ジェムズの契約ソングライターであったそうで、書く曲ははっきりしたメロディを持つものばかり。
演奏にはリオン・ラッセルの他、カール・レイドルやジェシ・エド・デイヴィスらが参加。アーシーなリズムセクションの上に美麗な管弦が絡む、ちょっと不思議な手触りのサウンドになっていて、リオン・ラッセルがハリウッドの腕利きセッションマン/アレンジャーとしての立場から、独立したアーティストへと踏み出そうとしていた微妙な時期であったことを反映しているよう。
アレンジにおいてはサージェントペパーに影響を受けたような凝りまくった展開が楽しいと言えばそうなのだけれど、やり過ぎて一聴しただけでは全体像が掴めない曲もあり。むしろ野心控えめの、比較的ストレートな曲調のものの方が良く出来たサンシャインポップとして聴けて好みですね。中でも "Good To Have You" という曲が抜群の出来で、ブライアン・ウィルソンが手がけたスプリングを思わせますよ。
なお、Now Soundsでは、これの前身グループであるガス・カンパニーの音源をまとめたものをリリースする予定もあるそうです。
2012-11-18
Gary Lewis & The Playboys / New Directions
ゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイズがキャリア後期に出した3枚のアルバムが、英BGOから3in2でCD化されました。
Disc1には1967年にリリースされた「(You Don't Have To) Paint Me A Picture」と「New Directions」の2枚のアルバムが収録。
まず「~Paint Me A Picture」はプロデュースにスナッフ・ギャレット、アレンジがリオン・ラッセルとお馴染みのチーム。
3曲のシングルヒットが収録されているのだけれど、個人的にはそのうち "Where Will The Word Come From" というのが大好きな一曲で。柔らかな管弦にコーラスも決まった、甘くジェントルなフラワーポップであります。ただ、それまでのシングルが全てトップテン入りしていたのに対して、ここでの3曲はそこまではいかず、そろそろ人気に陰りが見え始めた頃といえましょう。
その他の曲ではシングルB面であった "Tina" も良いのだけれど、この時期くらいまでの彼らのアルバムはシングル+埋め草、という感じのものが多くて。この「~Paint Me A Picture」でも有名曲・ヒット曲のイージーなカバーが多くを占めていて、それらはまあつまらないですね。"Barefootin'" や "Wild Thing" の出来ときたら腰抜け、という言葉が相応しい。
続いて出た「New Directions」、このアルバムが今回のリイシューにおける目玉でしょう。
ここではスナッフ・ギャレット=リオン・ラッセル組が外れ、ジャック・ニーチェ、ニック・デカロ、ハンク・レヴィンらによる制作となります。
収録曲のうち半分はアラン・ゴードン&ゲイリー・ボナーが書いたものなんだけれど、それがそのままアルバムの聴き所といえるのでは。いずれも洒落たセンスを感じさせる出来で、とりわけアルバム頭の "Girls In Love" "Double Good Feeling" とくる連打、及び最後を締める "Moonshine"、これらがダイナミズムと繊細さを兼ね備えたアレンジもあって素晴らしい仕上がり。
その他の曲でもラヴィン・スプーンフルを思わせる曲や、バーバンクサウンドと共通するような機知に富んだアレンジなど、聴いていて思わず頬が緩んできます。
全体として、それまでのゲイリー・ルイス&プレイボーイズの明るいイメージを残しつつも、ぐっと芳醇さを増したような印象で。穴埋め的な曲の無い、力の入った作品です。
Disc2はゲイリー・ルイスのソロ名義になる「Listen!」を挟んで1968年に出された「Now!」が収録。プロデュースにはスナッフ・ギャレットが呼び戻され、アレンジはアル・キャプス。
収録曲ではパレードがデモ録音を残している "How Can I Thank You" が目を引きますが、それよりもマイケル・Z・ゴードンの書いた "What Am I Gonna Do" がメランコリックで好みです。あと、ポール・レカの "Pretty Thing" も哀愁メロディと疾走感の対比が格好いい。
その他は殆どカバー曲ばかりなんだけれど、ここではそこそこ力の入った出来のものになっていて、中ではボブ・リンドの "Exclusive Butterfly" をメロウに仕上げたヴァージョンが気に入りました。
2012-11-11
アガサ・クリスティー「ひらいたトランプ」
紳士然としていながら、どこか悪魔めいた風貌のシャイタナ氏はエルキュール・ポアロに、自分は本物の殺人犯――罪を犯しながら逮捕されていない――を蒐集しているのだ、とうそぶきます。シャイタナ氏の招きを受けてパーティに参加したポアロであるが、その席上でブリッジが行なわれている間に事件が。容疑者はたった四人、そのうち誰がやったのか、そして本当に彼らは過去に殺人を犯してきたのだろうか?
1936年発表のポアロもので原題は "Cards on the Table"、作中では「手の札は開けて置く」と訳されており、手掛かりが公正明大であることを示しているのでしょうか。遊戯性が強く意識させられるタイトルです。
容疑者以外の登場人物には非ポアロものの作品『チムニーズ館の秘密』『七つの時計』で活躍したバトル警視、『茶色の服の男』からレイス大佐、パーカー・パインものにちょこっと顔を出していたオリヴァ夫人なども。ファンサーヴィスなんでしょうか、なんだか豪華な雰囲気でありますし、意外な犯人の可能性をあえて排除する狙いもあるのかな。
ミステリとしては物証が何もなく、機会は容疑者すべてにあるというかなり難しい設定であり、その分、人間心理に大きく頼った推理となっています。それでいてある程度納得させられてしまうのは大したものなのだが、ここは好みが分かれるところかも。
それより、強力なミスリードもあいまった、一転・二転する展開が見所で。非常に制約の多い条件下ですら、意外性を演出するその手際はお見事。
その他、序文からしてちょっとしたアイディアが隠されているし、コンセプトがはっきりと見えるのも面白い。アントニィ・バークリイを意識したような異色作ですね。
2012-11-10
The Who / Live At Hull 1970
二年前に出された「Live At Leeds」の40周年盤、そこに含まれていたハル・シティ・ホールでのライヴが単体でリリースされましたよ、と。
簡単におさらいすると元々は1970年に、ザ・フーはライヴ盤を制作しようという意図のもとリーズ大学とハルでライヴを行なったのだけど、ピート・タウンゼントがその録音テープを聴いて、ハルの方はレコードには出来ないな、と判断してお蔵入りにしていたそうな。
このハルでのライヴ、最初の5曲はベースが全く録れていなかったため、その部分はリーズのライヴから引っこ抜いてペーストしたらしい。そう聞かされても違和感がなくて。はっきりと気付くのは "Young Man Blues" においてリーズでのボーカルがうっすらリークしていることくらい。あと、もしかしたら該当曲でのギターの音がわずかに細くなっているかもしれない。
また、Disc 2の "Tommy" のパートではまるまる20秒の欠落があって、そちらもリーズから補填されたらしいのだが、いやはや、恐ろしいものだ。自分が聴いているものがどれくらい弄られたものなのかがさっぱり判らないぞ。
肝心の演奏自体は、前日に行なわれたリーズでのものと比べても結構ラフでミスもありますな。けれど「Live At Leeds」はデラックスエディション化された際、ノイズリダクションやイコライジングの影響でなんだか綺麗になりすぎてしまった、という気がするのだな。その点、このハルでのライヴはより生々しい感触に仕上げられていて、現代的に優れた音と言えるかも。特にドラムに凄く迫力があって、個人的にはそれだけでもこちらに軍配を上げたい。
しかし、フーのライヴというのは独特ですな。これだけラウドで荒々しいにも拘わらず、ポップソングとしての骨格は断固として堅持されているというのは、他のバンドにはちょっと無いのことなのでは。
2012-11-04
長沢樹「夏服パースペクティヴ」
昨年の横溝正史賞受賞作者による二作目。副題には「樋口真由”消失”シリーズ 少女洋弓銃殺人事件」とありますが、探偵役が共通する前作『消失グラデーション』を読んでいなくても、内容は独立しているため問題はありません。
廃校を改造したスタジオ、そこで学生たちの手によってプロモーションビデオが制作され、さらにその経過を追ったドキュメンタリー風(?)映画が撮影される。そんな、リアルと芝居の境界線を意図的にぼやけさせた場所で起こる事件。
前作が終盤に近づくまでがなんだかありがちなお話であったのに対して、今回ははじめからかなり変な状況設定。監督はカメラを止めたように見せて、気を抜いたスタッフたちを実はこっそり撮影しているとか。さらに廃校にまつわる幽霊なんかも絡んできて、いかにも何か仕掛けていそう。
そんな中でいくつか起こる不可能/不可解な事件。そしてその背後には、もっと大きな謎の存在が暗示されていく。
さらに後半に至り、麻耶雄嵩を思わせるような怒涛の展開が。
トリック一発の驚きでは前作に譲りますが、大技・小技を複数絡め、ミステリらしい雰囲気が濃厚になっていて、読んでいる間の楽しさではこちらが勝っているかと。謎が解かれた先に、背後に隠れていた物語が浮かび上がる、という趣向も三津田信三ばりに決まっています。
ただ気になったのは、確かに辻褄は綺麗に合うのだけれど、これは読者にとっては推理の余地が少ないものでもあって。伏線の判りにくさ、といってもよいか。ふ~ん、そんな細かいことをよく拾い集めたね、的な感想を持ってしまったのだな。
というわけで、前作に引き続き留保は付けてしまいますが、面白かったことは確か。とりあえず次も読むと思います。
2012-11-03
有栖川有栖「江神二郎の洞察」
江神二郎シリーズ(もしくは学生アリスもの)、まさに待望の短編集。
有栖川有栖が英都大学に入学してから二年生になるまでを描いた九編、書き下ろしひとつを含むそれら収録作品の発表時期には二十数年のスパンがあるのですが、今回、一冊のものとしてまとめられるに際して全作品に修正・加筆がなされているようで、違和感はないですね。
果たして次がいつ出るのか、そう考えると何だか読むのが勿体無いようでもあって。一編ずつ間を置いて読んでいきましたが。
もうなんていうか、いいね!
いや、このシリーズに関してはあまり客観的な言葉は出てこないのだな。
それでもあえてなんか書いて見ると、
冒頭の「瑠璃荘事件」では生活に根ざしたところに盲点があったり。シリーズのファンなら最後のパラグラフに悶絶必至だし。
一筆書きのような「ハードロック・ラバーズ・オンリー」。
「やけた線路の上の死体」ではトリックより細部を詰めるロジックが鮮やか。
「桜川のオフィーリア」の明白すぎる真相、という趣向。
ケメルマンの有名短編の向こうを張った「四分間では短すぎる」は「ミステリとは無為なもんや」を地でいく、遊び心満点の仕上がり。
肝試しの「開かずの間の怪」は馬鹿馬鹿しくも楽しいし。
「二十世紀的誘拐」はなんか作家アリスっぽい事件。
書き下ろしの「除夜を歩く」が一番、分量があるというのも嬉しい。内容も充分で、机上の空論の楽しみを堪能。また、江神部長のミステリ論はある意味、身も蓋も無いものなのだが、ジャンルに対する愛をびしびし感じさせるものだ。
最後の「蕩尽に関する一考察」はチェスタトンかな。
まあ、どれも良いんすよ。青春小説としての肉付けとミステリ部分の絡み方が凄く丁寧で。流したようなものがないです。
それにしても推理研メンバーたちが繰り広げるミステリ談義のなんと楽しげなことか。
限定された期間にのみ許された幸福な空間。なんだか切ない。
2012-11-02
Ray Terrace / Home Of Boogaloo
1968年リリースの、ニューヨーク出身のティンバレス奏者による、まろやかで楽しいブーガルー・アルバム。
演奏パーソネルのクレジットが無いのですが、基本的な編成はパーカッション、ベース、鍵盤に管が2本という割合シンプルなもの。その上に曲によってはヴォーカルが入ったり、インストではリード楽器がプラスされているといった程度なのだけど、ミックスが良いせいか物足りない感じはしないな。
アレンジを担当しているマーティ・シェラーは、モンゴ・サンタマリアやハーヴェイ・アヴァーン・ダズンも手がけていますが、それらと比べてもゆるめのサウンドです。
収録曲のうち、ヴォーカル/コーラスが乗ったものではポップなソウル色が強くなっていて、特にフランキー・ヴァリのヒット曲 "I Make A Fool Of Myself" は、原曲の洒落た味わいを残しつつも男性的な仕上がりが格好良い。フォー・シーズンズの持つラテン感覚を再確認させてくれる、これは良いカバー。
その他、"Listen To Me" はノーザンソウル風であるし、女性コーラスによる "You've Been Talking ´Bout Me Baby" は昭和歌謡を思わせる哀愁メロが悪くない。
一方でインスト曲のほうではラテン寄りのものが多いのですが、それらもコテコテのものではなくラウンジ仕様といったらいいか、クールでコンパクトな仕上がり。あまりラテンに馴染みがないひとでも取っ付きやすいのではないかな。
だらだらした休日の昼下がりなんかに良く合いそうな感じですな。
2012-10-27
エドモンド・ハミルトン「フェッセンデンの宇宙」
日本独自に編まれた短編集で、純粋なSFに限らず、ファンタジーや奇妙な味風のものまであって、分かりやすいお話が並んでいます。
中心になっているアイディアには、後にさんざん手垢をつけられてしまうものが多いのは仕方がないところですが、シンプルな形で提出されたそれらはプリミティヴがゆえの迫力のあるもの。むしろ、プロット部分でのひねり方に今となっては予想が付く部分が多く、時代的な限界を感じるかな。
全体に、簡潔な描写で異世界のイメージを喚起する力が素晴らしく、情感部分での肉付けがしっかりされていることもあいまって、充分に読めるものになっているかと。
印象に残った作品をいくつか。
「向こうはどんなところだい?」 地球に帰還した火星探検隊員は、亡くなった同僚の遺族たちに会う約束をしてしまった。だが、本当のことを話せるだろうか?仲間たちは過酷な環境の下、まるで虫けらのように死んでいったのだ。
読んでいてどうしたって火星と戦場を重ねてしまう、苦く、とてもアメリカらしい小説だと思う。
「凶運の彗星」 彗星接近と、それによって引き起こされた地球での異変の描写が迫力があって良かった。ただ、その現象の背後にあった意図が明らかになった後の展開は窮屈かな。
「翼を持つ男」 突然変異を扱った一編。何ということはない話ではあるが、寓意にとらわれず、ただ数奇な運命を描いただけの物語は美しい。結末は、そうでなくっちゃねえ、という感じ。
「太陽の炎」 宇宙探査局を辞めて地球に戻ってきた男。水星で見た何が彼を絶望させたのか。
異世界の燃え上がるようなイメージが素晴らしい。それだけに理に落ちたような締め方がちょっと残念。
「夢見る者の世界」 ザールという異界に住むジョタン族の王子、カール・カン。豪胆で快活な彼の生活には奇妙な秘密があった。
いきなりの意外な展開による掴みがいい。活劇の迫力も充分だし、結末も決まった。個人的にはこの作品がベストかな。
2012-10-24
アガサ・クリスティー「メソポタミヤの殺人」
1936年発表のポアロ物長編。イラクの遺跡調査隊を舞台にした物語で、クリスティの旦那が考古学者であったことを反映しているとかなんとかはまあどうでもいいや。
ある看護婦によって書かれた手記、という体裁を取っていまして。
「汽車のなかではよく眠れず、汽車のなかではよく眠れない体質なので、嫌な夢を見た。」
妙な文章だが。素人が書いた、ということでこうなっているのでしょうか。
命の危険を訴えている美しい夫人、しかしそれは虚言ではないのか? 最初はじわじわと不安を掻き立てていくのね、と思っていると急に一撃、ここら辺のチェンジ・オブ・ペースの呼吸は流石。
現場の状況はクローズド・サークルのようであるし(建屋の見取り図も挿入されている)、外部犯であれば不可能犯罪になる。ポアロは例によって人間性の謎を追っていくのだが。
真相はよくあるトリックを抜けぬけと使いながら、盲点を突くものになっている。だが、ポアロ自身が言うように物証が無い上に、伏線も少ないためちょっとカタルシスに欠けるし、唐突な印象すらある。その他、犯罪計画に色々と無理なところも目に付いて。意外性は充分なだけに詰めの甘さが惜しい。
ミステリとして面白いところはあるんですが、展開がちとルーティンワークっぽいかな。
クリスティ版旅情ミステリと思って読むべきだったか。
2012-10-22
大山誠一郎「密室蒐集家」
『アルファベット・パズラーズ』『仮面幻双曲』と、戦前の探偵小説家を思わせる世界感の作品をものしてきた大山誠一郎。その新作は密室殺人を扱った短編集です。
「あの、密室蒐集家ってどなたですか」
「いわゆる『密室の殺人』が起きると、どこからともなく現れて解決すると言われている謎の人物や」
ユーモア交じりでも何でもなく、大真面目な会話だ。この作者のものを今まで読んだことがなくて、これが受け入れられない人は向いてないかも。リアリティ? 人間を描く? 物語性?――いやいや、スッカスカだよ、潔いほどに。
手掛かりが全て提示されたら、すぐに謎解きが始まってしまう。小説家としての成熟を犠牲にして維持され続けたアマチュアリズム、これこそが魅力だ。
密室の趣向が一つ一つ違うのは当然として、密室状況が存在するという事実そのものに特別な効果を持たせたものもあって、なかなかに(ミステリとしては)現代的。
そして何より盲点を突き、いつのまにか倒錯の域へとずれていくロジック、その異様さが素晴らしい。本当は探偵が作者の代弁者で無い限りはそこまで断定できるはずがないのだけれど、短編としてなら成立しているというスタイルで。推理とともに事件の構図が反転していくスリルもたまらんねえ。
個人的なベストは「少年と少女の密室」かな。あるトリックの意外な使い方が新本格テイストで嬉しくなってしまった。
ゴリゴリのパズラーを読む喜び、ここにあり。
2012-10-21
Little Beaver / Party Down
マイアミのギタリスト/シンガー、1974年リリースのサードアルバム。
ゆったりとしたテンポに乗せて展開されるジャジーな和声感、メロウさを強調する鍵盤にブルージーでしなやかなギターの絡み。都会的な感覚といなたさの絶妙なバランスはマイアミ、という地ならではか。
リトル・ビーヴァーのヴォーカルは悪くないものの、本人が自分で思っているほどはうまくない、といった感じ。味のある声ではあります。
冒頭のタイトル曲 "Party Down" が群を抜いて素晴らしい。ざわめきによる演出も効果的に、パーティの終わり、というタイトル通りの雰囲気が描き出される。湿度を感じさせながらけだるくも心地いいサウンド。リトル・ビーヴァーの唄もここでは哀愁たっぷり、見事に決まった。
続く同曲の (Part Two) はインストヴァージョンで、高音を絞ったような丸みのあるギターが控えめにリードを取る。バックトラックだけでもずっと聴いていられそうな、いいグルーヴです。
他では "I Can Dig It Baby" が同じようにメロウながら、しっかりしたファンクとしても仕上がっていて、これも凄く好み。
最後に語りも入って、徹底してロマンティックに迫った "Let's Stick Together" でアルバムが締められると、いかにも軽いようでありながら後味は強く残る音楽だ、ということに気付かされる。一枚通して聴いても30分ちょっと、という短さも実はちょうどいいのかも。
2012-10-19
Donovan / The Hurdy Gurdy Man
1968年リリース。ドノヴァンがミッキー・モストと組んだアルバムの中ではこれが一番好きかな。
すっきりとして風通しがいいんですよ。これ以前にはまだ、陰鬱なフォークソング、ごてごてした管弦を背負った弾き語り曲なんかが幅を利かせていたのだけれど。このアルバムはなんか吹っ切れているようで、ドラムの入った曲の比率がだいぶ多くなっていますし、色々とポップな味付けはされていても整理がいいというか、それまでと比較して少ない工夫で大きな効果が上がっているという感じで。
冒頭に置かれた "Hurdy Gurdy Man" なんか、メロディだけ取ると展開に乏しい鼻歌みたいなもんですが、この曲にヒット性がある、と考えたミッキー・モストは偉かったんだ。エッジを効かせたバンドサウンドやタンブーラ、エコー処理でもってポップソングになっているのだから、本当、プロダクションの勝利ですよねえ。
もう一つのシングル "Jennifer Juniper" も童謡のような曲に、柔らかで控えめな管弦がちょうどいい塩梅です。
その他には、ジャジーなものやカリビアン風メロディ、もろインドかぶれの曲などあってヴァラエティにも欠きませんが、全体に軽やかな仕上がりが好ましい。
そして、アルバム終盤には穏やかで優しいアコースティックな手触りのものが並んでいて、流れも良いですね。
アルバム「Sunshine Superman」だけ聴いて、なんか古臭いなあ、眠くなってくるなあ、なんて思ったひとには試していただきたいな、と。
あと、現行CDのボーナストラックの中には「Greatest Hits」(1969年)のために再録された "Colours" と "Catch The Wind" も入っているのだけれど、これらも素晴らしく、当時のドノヴァン&モスト組の充実ぶりが伝わってきます。特に "Colours" は小船に揺られながら川を下っているような雰囲気がとても良くって、ニック・ドレイクを思わせるところもありますね。
2012-10-14
パトリック・クェンティン「俳優パズル」
パズルシリーズの第二作です。この作品は昔、旧訳で読んだことがあるのだけれど、そのときはあまり印象に残らなかったのだな。エラリー・クイーンの「国名シリーズ」の向こうを張った「パズルシリーズ」だと聞いていたので、さぞや凄いパズラーだろうと期待していたのがいけなかったか。
病気からの回復を果たしたピーター・ダルース。演劇プロデューサーとしての復帰をかけた舞台のリハーサルはしかし、最初からトラブル続き。ひとくせある俳優たちに、曰くある劇場。幽霊が目撃され、悪意ある何者かからの脅迫めいたメッセージが見つかる。そして、ついに死者までもが。
とにかく凄くテンポがいい。次々に過去の因縁や、意外な人物の繋がり、奇妙な謎が掘り起こされていきだれることが無い。そういった事件の解決に対する興味と同時に、舞台の成功を脅かすサスペンスが進行することでぐいぐい引き込まれて、まさに巻を措くあたわず。
また、ダルースをめぐる状態はかなり悲観的なんだけど、軽味を失っていないところも良いです。
そして、レンツ博士の古典的な名探偵ぶりは前作『迷走パズル』と比べてもずっと際立っていて。物語の進行に伴い、不可解な謎をひとつひとつ解いていく姿は堂々たるものです。
それでも事件全体を貫くものが明らかにされないまま迎えるクライマックス、このプレゼンテーションが実に鮮やか。ドラマ部分と謎解きがぴたり、と嵌った格好良さはグレイト!、のひと言。
大トリックや精緻なロジックはありませんが、非常にうまく組み立てられたミステリでした。面白かった。
2012-10-09
Betty Wright / I Love The Way You Love
ヒット曲 "Clean Up Woman" を収録したベティ・ライトのセカンドアルバム、1972年リリース。
制作はマイアミで、クラレンス・リードやリトル・ビーヴァーが中心になっており、曲も二人のいずれかが書いています。
とにかくキャッチーなメロディのものが揃っていて。中でも "If You Love Me Like You Say You Love Me" という曲は'60年代モータウンを思わせるし、スロウの "I'm Gettin' Tired Baby" でも展開には一捻り。
その他、ファンキーで乗りのいい "All Your Kissin' Sho' Don't Make True Lovin'"、南部風の "Pure Love" などアレンジのヴァラエティも上々。
唯一のカバーがビル・ウィザーズの "Ain't No Sunshine" で、オリジナルのイメージをしっかり残しながらも、ぐっとメロウなテイストを付け加えることに成功していて、これも良いな。
この頃、まだベティ・ライトは十代であったのだけれど、デビューが早かったこともあってか、既に堂々とした唄いっぷりを聴かせてくれます。ポップな題材との相性も良かったのだろう、若々しい勢いは感じさせながら、それが拙さに繋がっていない。
個人的なベストは "I'll Love You Forever Heart And Soul"。美しいトラックとテンション高めの歌唱の組み合わせがアリス・クラークにも通じるようでありますよ。
2012-10-08
エラリー・クイーン「フランス白粉の謎」
しかし――」その言葉は、すさまじい勢いで皆に襲いかかった。「――実はもうひとつの推理も引き出されるのです――ただひとりを除いて、すべての容疑者を一気に除外してしまう推理が・・・」眼に炎が燃え盛った。声からかすれが消えた。エラリーは慎重に身を乗り出し、机の上に散乱する証拠品越しに、彼自身の引力でもって一同の注意をしっかりとひきつけた。「すべての容疑者を――ひとりを除いて」ゆっくりと繰り返した。
国名シリーズ新訳の第二弾です。
もう何度も読んでいる作品なのであるけれど、うん、やはりいいですね。
最初の100ページほどを占める第一部ではまだデビュー作『ローマ帽子の謎』がそうであったように、警察小説としてのフォーマットが守られているようだ。クイーン警視による尋問の様子は事細かに描写されているし、捜査に上役からの横槍が入ったり。
それが第二部に至ると、アマチュア探偵エラリーが友人をワトソン役に立てて、独自に現場を調査する。ここに至って本格ミステリとしての興味が俄然高まってくるし、前作『ローマ帽子の謎』にあったような構成上の単調さが回避されている。『ローマ~』の実質的な主人公がリチャード・クイーン警視であったのに対して、ここからがエラリーが中心となった物語なのだ。
死体の奇怪な出現による発端から次々に事件の主眼が動いていく展開も見所。そうしたプロットの充実が都会的な設定に見事に落とし込まれていると思う。
ロジックには後の作品と比較すると蓋然性に寄りかかったような箇所が目立つのだが、推理そのものによって生み出されるドラマが素晴らしい迫力で、これこそがクイーンの真骨頂だ。
もったいぶった気取りさえ、二十代半ばの作者の手によるものだと考えるとチャーミングに思える。実に洒落ていて、最高に心地の良い手触りにはしかし、僕が好むような読み物は現代では既に死に絶えたものである、ということを思い知らされるようでもある。
次作『オランダ靴の謎』は2013年刊行予定、ということなのだが、ひょっとして年一冊のペースなのだろうか。
2012-09-24
ジェデダイア・ベリー「探偵術マニュアル」
常に雨が降り続ける都市の探偵社、そのベテラン記録員アンウィンはある日突然に、探偵への昇格を命じられる。そして、何かの間違いでは、と上司を訪ねたところで死体を発見してしまう。渡された「探偵術マニュアル」と眠り病の助手を頼りに事態の収拾に努めるうち、アンウィンはいつしか奇怪な陰謀の中に巻き込まれていく。
・・・と書くといかにもミステリっぽい筋立てでありますが、これはファンタジー作品と言ったほうがいいかな。
もういい年のはずなのに少年のような心を持つ主人公アンウィン。不条理感漂う探偵社のルール。夢遊病者が集まるパーティ、カリガリ・サーカス、町中からかき集められた時計。そして伝説の怪事件。
キャラクターたちはそれぞれが裏の顔を持ち、謎めいたセリフを残していく。
どう進むつもりなのか見当がつかない展開には本当、わくわくさせられる。
事件の全容が明らかになっていく後半の雰囲気は、ほのぼのしたフィリップ・K・ディックといった感じで、繰り広げられる奇妙なイメージが魅力的です。
一方で、ミステリとしての筋道がこの作品をしっかりとエンターテイメントの枠内に落とし込むことになっていて。拡げた風呂敷はきっちり畳まれている、というわけ。
博物館の中で開陳されるチェスタトン的なトリックには、思わず頬が緩みました。
ジャンルにこだわらずに面白いものを読みたい、というひとにはいいでしょう。
BGMは10ccの「How Dare You!」というところで。
2012-09-23
ダシール・ハメット「マルタの鷹〔改訳決定版〕」
これも創元・早川両方の版で何度も読んだ古典だ。以前に早川から出ていたのも小鷹信光による翻訳だったのだが、改訳ということで。
どこか悪党めいたところのある探偵二人と、身なりが良く若い女性の依頼人。駆け落ちした妹探し、といういかにも私立探偵小説らしい発端は、程なく血腥く欲望にまみれた展開へとなだれ込んでいく。
「あんた方にも警察にも、いうべきことは何もない。市から給料をもらっている町中のいかれた連中に、あれこれ非難されるのも飽き飽きした。今後おれに会いたければ、逮捕するか召喚状を持ってこい。そうしたら弁護士を連れて会いに来てやる」
サム・スペードが地方検事に言い放つ科白だ。随分と勇ましい。お偉方に対してこんなにも強く出られる私立探偵が実際にいるだろうか。
あるいは結末近くでの大演説。自分の心の揺れを何から何まで説明してしまう。まるでメロドラマだ。
だが、ハメットのようなオリジナルなものに、ジャンル小説としてどうこう、というのは無意味なことかもしれない。
実をいうと作者自身による序文において、スペードはこうありたいと願った理想像である、ということがはっきりと書かれているのだ。
殺された相棒に対して、サム・スペードが実のところどう感じていたのかは読者にはなかなか窺い知れない。今更こんなことを書くのもなんだが、そうした「行動によって語らせる」そのままに、心理描写を排除した文体によって醸される緊張感とリズムが心地良い。
ハードボイルド云々、はいったん頭から退けて、まずはその格好良さにやられて欲しい。
真に力強いミステリだ。
2012-09-17
The Clash / London Calling
僕にとってパンク、というのは他と違うことをやることであって、つまりニューヨークのそれ。みな音楽的には見事にバラバラでありました。対してロンドンパンクというのはつまるところは下手糞なロックンロールのこと。
クラッシュというバンドはアルバムを追うごとに達者になっていき、当然のようにパンクではなくなっていった、なんていうと怒る人はいるだろうな。どうでもいいが。
ドラマーこそが肝だ、とつくづく思う。
「London Calling」は1979年リリースの三枚目。
タイトル曲は今となれば結構、野暮ったく思えるのだが、他は数曲のカバーも含め、みんないい。アナログ二枚組のサイズを弛み無いナンバーで埋め尽くしたという点でこのアルバムは、ストーンズの「Exile On The Main Street」に肩を並べるものなのでは。
アレンジは意外な振り幅の大きさに楽しくなってくるもので、スカやレゲエのような曲調だけでなく、ブラックミュージック色濃いもの、さらにはロカビリーや'60年代ガールポップ風のものまである。そして、そういった雑駁さがキズになっておらず、どれを取ってもクラッシュらしさ、というものが感じられる仕上がりだ。
また、ストレートなロックンロールでもシャープでなおかつ微妙なニュアンスがあって、懐の深さを感じるようになってきている。
ルーツに対する愛情とバンドの持ち味であるソリッドさが見事に結びつき、躍動感が伝わってくるこのアルバム。クラッシュのようなバンドにはふさわしくない言葉かもしれないが、ロックンロールに新たな多義性をもたらしたクラシックだ。
とはいえ、秀逸なカバーデザインはそもそもこの作品がロックンロールを終わらせるべく企てられたことに呼応しているらしいのだが。そう考えるならクラッシュはやはりパンクだったか。
2012-09-16
Billy Preston / Club Meeting
ビリー・プレストンが1967年に出したライブ盤、なのだが。
僕の手元にあるのは前年に出た「The Wildest Organ In Town!」とカップリングされたCDで、これ以外の形態で「Club Meeting」というアルバムは見たことがない。オフィシャルのディスコグラフィーにも「1967 Club Meeting」とは書いてあるのに、ウェブ上でいくら検索してもアナログ時代のジャケットは見つからなかったし、持っているという記事も無かった。言ってもそれなりに名前のあるミュージシャンで、しかもキャピトルから出たものなのだから、たとえばeBayあたりで何かしらヒットしそうなものだろうに。
ただ、この「Club Meeting」に入っている二曲をカップリングしたシングル盤はちゃんと存在するようだ。ひょっとしたらプロモオンリーとかの類のアルバムなのだろうか。
で、このCDなのだけど。ライブが録音された時期や場所も記載されてないというなかなか厄介なものだ。しかし、内容はいいぞ。インストと唄物が混在するR&Bショウで、観客の盛り上がりも相当に熱い。実は黒人婦女子のアイドルだったのかしら、というくらい。
「The Wildest Organ In Town!」では曲のキメのフレーズを叫ぶくらいであったビリーだが、ここでは堂々としたボーカルを聞かせてます。ジェイムズ・ブラウン・メドレーでは鍵盤を離れての唄いっぷりまで。
勿論、オルガンの方も全開で。中でも、スタンダードの "Summertime" ではまずいったん奔放なプレイを見せたあと、「ベートーヴェンならこんな風かな」と言うとクラシカルなフレーズを披露、さらに「レイ・チャールズが演ってるのを想像してみて」と言うやホーンセクションを従えた熱演。
謎のコーラスグループがまるまる一曲唄うものなんかもあって、全体としてはとっちらかった内容なんですが、それも含めて'60年代的な熱気がパッケージされたライブ盤だと思います。
後にアップルからの「Encouraging Words」にも収録されることになる "Let The Music Play" は、ここでのヴァージョンの方が数段格好良いですぜ。
2012-09-11
倉阪鬼一郎「不可能楽園〈蒼色館〉」
倉阪鬼一郎による年に一度、恒例のバカミス。
今回は鉄壁のアリバイ+誘拐劇+衆人監視下の消失、といったところであって、例によって凄いっちゃあ凄い密度です。
アリバイトリックは複合技を使っているせいか、例年に比べると破壊力がおとなしめではありますが、脱力感は充分。
また、それに絡めてある錯誤が仕掛けられていて。読んでいても違和感というより、明らかにおかしいだろうというレベルのものなんですが、真相の馬鹿馬鹿しさはこちらも負けず、なおかつ古き良き新本格テイストも感じられる絶妙の効き方をしています。
勿論、丁寧に張り巡らされた伏線は笑いを誘わずにはおきません。
事件の謎が解かれてから以降、終盤の怒涛の展開は、まあ、毎回似たようなものなんですけれど。予想だにしないが特に驚きもない、という。ただ、今作ではその部分がややあっさり目であって、その分、小説としてのまとまりが良いように思います。
いや、むしろこの綺麗な閉じ方に、ある種のミステリの終着点を感じる、なんて言い過ぎかしら。
そうだ、帯の文章は先に読まない方がいいかも。
2012-09-09
アガサ・クリスティー「ABC殺人事件」
「エルキュール・ポアロ氏へ
あんたは頭が鈍いわれらが英国警察の手にあまる事件を解決してきたと自惚れているのではないかね。お利口さんのポアロ氏、あんたがどこまで利口になれるかみてみようじゃないか。たぶん、この難問(ナッツ)は、固すぎて割れないことがわかるだろう。今月二十一日のアンドーヴァーに注意することだ。」
ポアロの元に届いた手紙、それが連続殺人事件の始まりだった。アルファベットの順に選ばれる被害者、必ず現場に残されるABC鉄道案内。送りつけられる殺人予告状を前にしても、未然に犯罪を防ぐ手だては無いようだった。
1936年発表で、クリスティの代表作のひとつでしょう。ミッシング・リンク&シリアルキラーものの古典であり、女史の作品としてはかなり派手というか扇情的な道具立てであります。
犯人はおろか次の被害者の手掛かりのないままに、殺人が繰り返される。そのため、途中までは謎説き小説というよりはノンストップのサスペンスノベルとしての色が濃い。
そして、ヘイスティングズによる一人称の語りの間に謎の人物を描いた三人称が挿入される、という構成もいかにもこの手の作品の先駆らしいが、それはミステリとしての必然性があるものだ。
この作品で描かれている極めて人工的な犯罪は、批判にさらされることも多いですが、作者自身もそこは自覚しているようで、周辺を補強するようなさりげない辻褄にも配慮されています。
アイディアの貧困を人間ドラマで糊塗しようとする作品など、そもそもミステリではないだろう。そう思っている僕のような人間には、貪欲なまでの騙しの姿勢こそが嬉しいし、細かいミスリードも例によって効いている。
何より、この分量でこの内容というのが凄いではないか。
再読ですが、面白かった。
2012-09-08
The Mamas & The Papas / People Like Us
ママズ&パパズが一度解散した後、ダンヒルとの間で残っていた契約を消化するため作られたアルバムで、リリースは1971年。
昔はこの作品はあまり好きではなかった。なんだか張りがなくて、かったるいと思っていたのだ。
最近、英Now Soundsからリマスター盤が出たので、聴き直してみた。すると・・・。
一曲目の "People Like Us" を聴いて、おお、こんなに格好よかったっけ、と思ったのだね。それ以降の曲も、いいグルーヴのものが続く。これはもしかしたら凄いアルバムだったのか。
しかし、最後まで聴き進めていくうち、う~ん、と考えてしまった。
問題はソロボーカルですね。キャス・エリオットがあまり目立たず、かわりに多くの曲ではミシェル・フィリップスがリードを取っているのですが、個々の曲として聴くにはいいものの、アルバムを通して持たせるにははっきり言って、弱い。どんなタイプの曲でもこなせる、といったシンガーではないのだ。また、どういうわけかデニー・ドハーティもここでは、ただ優しげなだけだ。そのせいで、"Pearl" という曲でママ・キャスのしっかりしたリードが聴こえると、ほっとする。
ハーモニーボーカルの部分では何の問題も無いのだけれどね。
とはいえ、昔思っていたほど悪いアルバムではないという気がしたのは、リマスター効果かこちらの趣味が変化したからか。
サウンドはとてもいいのです。かつてのフォークロックとはまるっきり違い、都会的でメロウなR&B色濃いもので。デヴィッド・T・ウォーカー、ジョー・サンプル、エド・グリーン、ボビー・ホールらによる演奏には文句無し。
全てジョン・フィリップスの手による楽曲のほうも、抜けの良いものはありませんがそこそこ悪くない出来だと思う。
サンシャインポップというより曇り空、翳りあるポップスで。ソフト&メロウなものが好きな人なら気に入るんじゃないでしょうか。あるいは'70年代前半の、ソウルの影響を受けたシンガーソングライター作品の先駆け、として扱うのが正しいのかもしれません。
2012-09-03
Dionne Warwick / Make Way For Dionne Warwick
ハル・デヴィッドが亡くなったそうだ。91歳ということで、ブリル・ビルディング界隈のライターの中でも、ロックンロール以前の世代に属するひとであった。
「Make Way For Dionne Warwick」はセプターから1964年にリリースされた、ディオーン・ワーウィックのサードアルバム。
バカラック&デヴィッドとの蜜月期、そのうちでも特に収録曲の充実が半端ない一枚だ。
ヒットシングルが四曲、"A House Is Not A Home"、"You'll Never Get To Heaven (If You Break My Heart)"、"Reach Out For Me".、そして "Walk On By"。
それ以外にも、ダスティ・スプリングフィールドのカバーが有名な "Wishin' And Hopin'" と "Land Of Make Believe"、カーペンターズがヒットさせた "They Long To Be Close To You" などなど。
僕がバカラック&デヴィッドの書いた曲を探求していたのは、もう随分昔のことだけど、久しぶりに聴いてみても、やはり感心するばかりで言葉がないわ。足りないものも余分なものも無いようだ。
"They Long To Be Close To You" はどんなカバーより、ここで聴ける密やかな感じのものがずっといい。
しかし、昔のポピュラーシンガーというのは、発音がはっきりしていて気持ちがいいですね。うまく唄おう、聴き手を感心させようということよりも、作・編曲者の意図を実現することが第一にあったからではないかしら。
ところで、このブログの名前は "Walk On By" の歌詞の一節から取ったのだけれど、この曲に関してはビーチ・ボーイズのヴァージョンが一番好きなのだな、実は。
2012-09-02
Dee Felice Trio / In Heat
ジェイムズ・ブラウンのジャズ仕様アルバム、「Getting Down To It」でバックを務めていたピアノトリオによる唯一のアルバムが、国内初CD化されました。
オリジナルのリリースは1969年、キング傘下のジャズレーベルであるベツヘレムで、JBもそこからシングルを出したことがあります(*)。
硬質なドラム、よく唄うベースにアタックが強く、余韻を生かしたピアノ。曲によってはリズムギターや管弦も入っていますが、JBが目をつけたのも頷けるようなしっかりと芯のある、いいグルーヴの演奏です。
全体の半分ほどが有名曲のカバーで。"The Crickets Song" はマルコス・ヴァーリ作のサンバですが、ドラムブレイクもあって渋格好良い。"There Was A Time" はご存知JBのヒット曲。ファンクとまではいきませんがループ感を演出するギターとホーンが入って、なかなか乗りもいい。
中でも特に気に入ったのはグレン・キャンベルのヒット曲 "Wichita Lineman" とジョニー・ミッチェルの "Both Sides Now" で、力強くも流麗なピアノが映える美しい仕上がり。
そしてピアノのフランク・ヴィンセントの手によるオリジナルが四曲あるのですが、演奏の躍動感ではカバー曲よりむしろこちらの方が勝っているかな。タイトながら瀟洒なジャズボッサで、いや実に格好よくスウィングするもんだ。
ボーナストラックの3曲はシングルオンリーだったもので、アナログ起こしらしいノイズがパチパチいってます。まあ、レアなものですからね。"There Was A Time" はイントロが格好いい別ヴァージョン。他の2曲は、よりジャズらしい演奏といえましょうか。
2012-09-01
Elvis Costello and The Attractions / Goodbye Cruel World
1984年、エルヴィス・コステロがモダンなソウルミュージックに近いスタイルを試みたアルバム。プロデュースは前作「Punch The Clock」に続いて、クライヴ・ランジャー&アラン・ウィンスタンリー。
コステロ自身は昔からずっと、このアルバムのコマーシャルなサウンドについて良いことは言っていないが、僕の個人的な好みとしてはそれほど悪くないと思う。本人がどう思っているかは別として、少なくともコステロにはもっと他に引きの弱い作品があるだろう。
確かに派手なシンセの多用が時代を感じさせる瞬間もあるんだけれど、逆にあまり大した起伏のない曲でも単調さに陥らずに聴けるものになっている面もあって、流石にマッドネスのプロデューサーは違うな、と。
実際、このアルバムの曲のシンプルなデモや弾き語りヴァージョンを聴いてもそんなに面白くない。エルヴィス・コステロというひとはもしかしたら歌はうまいのかもしれないけれど、いかにも不十分だ。プロダクションの工夫が足りないものでも聴かせられるのは、天性の魅力的な声を持つようなほんの一握りのシンガーのみだろうと思うのだが。
オープナーの "The Only Flame In Town" なんかは、ライヴだとスロウにして思い入れたっぷりに唄っちゃったりされますが、スタジオヴァージョンでの弾むようなリズムに乗ってこそポップソングとして成立しているんじゃないかな。
メロウな佳曲が多いけれど、サウンドとの親和が一番いいのはカバーの "I Wanna Be Loved"。コード感を強調することで、ティーチャーズ・エディションのオリジナルよりもずっとフックが効いたものになっている。やっぱりベースはブルース・トーマスがいいね。
時代の音としっかり向き合うことで、エルヴィス・コステロのアルバムの中でも特に親しみ易いものとなっている作品では。
2012-08-29
Ninapinta / The Downtown Scene
1965年、ヴァージン諸島出身のパーカッショニストによる唯一のアルバム。
ニューヨーク録音で、ラテン・ラウンジ・ジャズとでも言いましょうか。全編、陽気でリラックスした雰囲気の演奏です。
ポップスファンにはジェリー・ロスとの仕事でお馴染みなジミー・ウィズナーがアレンジャーであり、鍵盤も弾いています。曲によっては、ドラムでゲイリー・チェスターが入っている安心のグルーヴ。
取り上げられている曲はみな、当時の大ヒットばかりであって、オールディーズファンなら大概、聞き覚えのあるメロディが次から次と出てきます。フォー・トップスの "I Can't Help Myself" の中で、"Watermelon Man" のフレーズが飛び出したり、ペトゥラ・クラークの "Downtown" ではドリフターズの "On Broadway" が織り込まれていたり、なんて遊びも。
ニーナピンタというひとにはこれ以外に録音は残っていないようであります。最初に書いたヴァージン諸島云々はスリーヴノーツに記載されていたことなんですが、当人に関する写真や情報はまるで見当たらず、そもそも実在した人物なのかが定かでない。
一方で、モンゴ・サンタマリアの変名では、という説もありまして。クリストファー・コロンブスの率いていた三隻の船の名がニーナ号にピンタ号、サンタマリア号であったことに引っ掛けて付けた名前だ、ということなんですが、さて。
ヒップとかクールという感じではないですが、やりすぎず、ちょうどいい湯加減が魅力ですな。ソウル寄りのものはブーガルーとして楽しく聴けます。
プロフェッショナルによる手堅い仕事、和みの一枚。
2012-08-16
Follow Me (original soundtrack)
1969年にユニ・レーベルからリリースされたサーフィン映画のサウンドトラックで、手がけたのはスチュ・フィリップス。我が国でも数年前にCD化されましたが、しばらく入手困難になっていました。
で、最近になってサントラ専門のReel Timeというところからストレートリイシューされたのですが、これアナログ盤起しのようです。特に音が悪いって程じゃないけど。ライナーノーツには、原盤権利者が見つからなかったのでエスクロー・アカウントを立ててどうこうして、とりあえず出しちゃいました、なんてことも書かれてまして。日本盤を持ってるひとは買い直す必要は無いんじゃないかな。
内容のほうですが。サーフィン映画といっても、音楽はあんまりそんな感じがしない。まあ、'69年ですからね、流石にリバーブ全開のギターとか、ビキニのお姉ちゃんとGO! なんて時代ではないです。レイドバックしたリゾートミュージックってところですか。
ポップスファンには、ディノ・デシ&ビリーがボーカルを取る四曲が注目ですね。まあ、歌はそんなにうまくないんだけれども。やはり、デヴィッド・ゲイツが絡んだ "Thru Spray-Colored Glasses" が頭ひとつ抜けてますが、もうひとつのゲイツ作 "Just Lookin' For Someone" も甘すぎず悪くない出来。
また、その他を占めるインスト曲もいかにも'60年代らしいカラフルさと軽やかさが好ましいもの。フルートやヴァイブを生かした美麗できらきらしたサウンドに、エキゾティックな味付けがバラエティを与えていて。特にスキャットコーラス入りの曲はポップスファンでも充分に楽しめるかと。
そろそろ終わりかけの夏に相応しい一枚とかなんとか。
2012-08-15
アガサ・クリスティー「雲をつかむ死」
エルキュール・ポアロものの1935年発表長編。
パリからロンドンへ向かう旅客機内で、まもなく目的地に着こうかというときに老婦人の死体が発見される。その死因は南米の吹き矢による毒殺らしいのだが、どうやら誰にもそれを使う機会は無かったようなのだ。
これまでの作品で、列車を閉鎖空間として扱ったものはあったが、今度は旅客機でやったというところかな。もっとも、こちらは乗客たちの相互監視の目がずっと強く、そのことがミステリとしての難度を決定しています。
ジャンル小説としての純度は非常に高く、人物紹介を手際よく済ませるとすぐに事件が起こってしまう。60ページにはすでに検視審問がはじまるのだから進行が早い。その後はずっと、ポアロとジャップ、そしてフランスの警部の三人が頭を突き合わせながらの捜査が続くのだが、わざとらしくないユーモアの加減もあって、退屈せずに読んでいける。このあたり、ワンパターンなのだろうが、読者にストレスをかけない流れはもう名人芸といっていい。
不可能犯罪としての興味もありますが、その辺の検討は置いてけぼりで、いつものポアロものと同じく人間性にまつわるあれこれでお話は進んでいきます。
最後に明かされる真相はごくシンプル。当たり前過ぎるがゆえの盲点を突いたスマートなもの、と言いたいところなのだが、冷静に考えると相当無理がある。もっと大きな無理筋のものをミスリードにしているので、見逃してしまいそうになるが。
着想は良く、抜群の技術の冴えも見せながらも、詰めが甘い。そんな感じですかね。
2012-08-14
チャイナ・ミエヴィル「都市と都市」
架空の現代都市を舞台にしたSFだが、設定が恐ろしく奇妙でかつ魅力的なもの。
その領土が複雑に入り混じり、ときには同じ空間を共有してさえいるふたつの国「ベジェル」と「ウル・コーマ」。異なる文化や言語を有するだけでなく、国民たちはそこに存在するもうひとつの国の建物や人物を直視することが禁じられている。そして、他国の領域を侵犯した者は、不可蝕で超越的な外部権力「ブリーチ」によって除去されてしまうのだ。
こうやって説明すると不条理というか頭でっかちっぽいのだけど、作品内ではしっかりと描写されることによって、なんだかありそうなものとして受け入れさせられてしまうのが凄い。
そんなベジェルにおいて女性の刺殺死体が発見されるのだが、国内には被害者に該当する人物が見つからない。一体、彼女はどこから来たのか、そして、犯人は誰なのか。やがて、捜査の過程で浮かび上がってきたのは、伝説上の第三の都市。
正直、あまりとっつき易い小説ではない。また、作品内で世界のルールを丁寧に説明してくれるわけではないので、自信の無いひとは先に解説に目を通しておいたほうがいいでしょう。
けれど、読み進めていくと途中からは都市の持つ謎と殺人事件の捜査が有機的に絡みあって、ぐいぐいと引っ張られていく。
そして後半、物語の様相が一転・二転。「プリズナーNO.6」を思わせるところもあって、ミステリなんだかSFあるいはファンタジーなのか、プロット上の落としどころをどういうレベルでつけるのかが、最後まで見当がつかない。
いや、無茶な世界を破綻無く書ききった力作ですな。筋を追うことに汲々としていては楽しめないかも。まずは異世界ものならではの醍醐味を堪能していただきたい。
2012-08-05
Cal Tjader / Soul Burst
1966年、ヴァーヴからのリリース。プロデュースはクリード・テイラー、録音にルディ・ヴァン・ゲルダーとお馴染みのチーム。
軽快なラテンリズムと流麗なメロディが良い塩梅で、クリード・テイラーらしく耳当りは良いがユニークなアルバムになっています。勿論ヴァイブが主役なのですが、フルートが大きく絡むことで、メロウさが強調されているのではないかな。
ピアノを弾いているのがチック・コリアなのだけれど、パーカッシブとさえいえるアタックを感じさせる演奏はラテン色の補強に一役買っているよう。特に、短い曲だけれど "Descarga Cubana" では同じリフが延々繰り返されているのをバックに、彼の一人舞台といったところです。
なお、タイトルに反してアルバムのどこを取ってもソウル色は皆無。「Soul」と銘打てばちょっとは売れ行きが良くなるのでは、という思惑でもあったのかと。
アルバム全10曲中、ラテンパーカッションだけでなくドラマーも参加しているものが4曲あって。目立たないプレイに終始しているのだけれど、昭和歌謡っぽい哀愁メロディの "Cuchy Frito Man" とディジー・ギレスピーのクラシック "Manteca" は、それでもリズムが強調されたごきげんなミディアムに仕上がっています。特に "Manteca" は、コンパクトにまとまった曲が多いこの盤にあって比較的に尺が長く、グルーヴに乗ってどんどんと演奏が続いていくさまが気持ちいい。
また、クルト・ワイル作のものが2曲取り上げられていますが、ともに穏やかなスロウ。うち、"My Ship" はラテンというよりボサノヴァですね、もう。ここら辺、クリード・テイラーの入れ知恵なのかな?
乗りがいいのが聴きたいけど暑苦しいのは嫌だ、というワガママな要求に答えてくれる一枚ですな。
2012-07-31
カーター・ディクスン「黒死荘の殺人」
『プレーグ・コートの殺人』のタイトルでも知られる、ヘンリ・メリヴェール卿初登場作の新訳です。これも大昔に一度読んだきりでありましたが「そういえばこんな話だったか」程度には覚えていました。
今作品においては、怪奇小説としての色付けが特に強いです。事件が実際に起こるまで100ページほど、じっくりと雰囲気を煽り立てていきますが、これが退屈にはならず結構読ませる。マスターズ警部に偽霊媒の使うトリックなど語らせながら、それでも拭えない不気味さが高まっていきます。
そして起こる殺人事件はかなりの不可能犯罪。堅固な密室のうえ、建物周囲の地面に足跡が無い。捜査するほどに状況の不可解さが明らかになっていくようで、マスターズたちはすっかり途方に暮れてしまいます。
物語半ば過ぎになってようやくH・M卿が登場するのですが、そこで物語の雰囲気は一旦、がらりと変わります。不気味な様相は一掃、謎解きの興味が前面に。
密室の謎はまだ残しながらも、事件のみせかけに惑わされていた関係者たちの蒙を啓く鮮やかさは、流石のひと言。
しかし、更なる事件が起こり・・・。
いや、本格ミステリとして面白さ全開の展開です。なおかつ最後に明らかにされる真相は相当に意外なもの。
一方で、トリックを知った状態で読んでいても、あまりに手掛かりが弱い、という気はします。また、初期のカーらしく、非常に独創的なアイディアが用意されているかわりに、細部の辻褄はややこしくて一読ではすぐに飲み込めないかも。
ひっくるめてカーのある面での代表作であるといえましょうか。
なお、ダグラス・G・グリーンによる序文がついているのですが、これが美辞麗句が踊っているだけのようなものではなく、しっかりと力のこもった内容。本作『黒死荘の殺人』に辿り着くまでのカーの作品における幽霊趣味について非常にわかりやすくまとめられていて、面白いです。
登録:
投稿 (Atom)