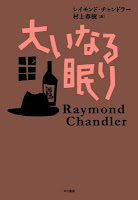2012-12-31
アガサ・クリスティー「もの言えぬ証人」
多くの財産をもつ老婦人エミリーとそれにたかろうとする浪費家の姪や甥たち。やがて身の危険を感じる出来事が起こり、エミリーはエルキュール・ポアロに手紙をしたためる。だが、実際にポアロの元に届いたそれは、書かれてから二ヶ月後に投函されたものであった。事件の可能性を見て取ったポアロはヘイスティングズとともに夫人の住む屋敷に向かった。しかし、彼女は既に亡くなっており、その財産の殆どは親族ではなく身の周りの面倒を見ていた家政婦に残されていたのであった。
文庫本で500ページほどあって、いままで読んだクリスティ作品のなかで一番長いお話かな。タイトル『もの言えぬ証人(Dumb Witness)』は被害者の飼っていた犬を指しているようで、本書の献辞もクリスティの愛犬ピーターに捧げられています。
そもそも犯罪があったのかさえはっきりしない状況が扱われていて、なかなか推理の取っ掛かりがない。気が付けば300ページくらいまで読み進めているのに、未だ雲をつかむような話のままなのだ。それでも、ちょっとしたフックで興味を繋いでいき読者を退屈させない手際は、いつもながらに大したものである。
また、ヘイスティングズの存在による牧歌的な雰囲気が特に強く感じられるのだけれど、彼はこの作品を最後にお役御免となって、その復帰はシリーズ最終作『カーテン』まで無いようですね。
大詰めにおける推理は物証が無いゆえに性格分析に大きく頼るもの。関係者の不可解な行動を心理から解き明かす部分はなるほど、さすがと唸らされるものでありますが、その反面、犯人絞込みの説得力は乏しい。ただフーダニットとしての興味とは別に、女史の作品では珍しい趣向があって、これが面白い。
犯人当ての興趣には欠けますが、非常に独創的な構図を持つ物語であります。結局、公的には何の事件も起こっていないのだし、殺人が行なわれたことすら証明するものはポアロの言葉以外に無いのだから(それが意図的なものであるのは、小説内に警察官が一度も登場しないことからも明らかでしょう)。
2012-12-30
Satisfaction Unlimited / Think Of The Children
サティスファクション・アンリミテッドというボーカルグループがホランド=ドジャー=ホランドのホット・ワックスから1972年にリリースした唯一のアルバム。
ノーザンといえばそうなのだが、ホット・ワックス/インヴィクタスと聞いて考えるようなものとはまるっきり違う音であります。結構、例えようがない個性というか。あえて言うなら'60年代のテンプテーションズがニューソウルを演っている、という感じ。
メンバーには'50年代の終わりから活動しているひともいるようで、ドゥーワップを根っこに持つような端整なコーラスに、良い声で温かみのあるリードで、オーソドックスながらバランスが凄くいいです。
曲のほうはミディアムが殆どだけれど、ダンサーよりもメロウさが際立つ仕上がりのものが多い。といっても甘すぎず、しなやかで包み込むようであって、気持ちよくグルーヴに浸っていられる。これもまたソウルミュージックの魅力であるよね。
強烈な持ち味は無いようでいて、実は似ているものが他に見当たらない音楽では。
非ソウルファンにも聴いてもらいたい一枚です。
2012-12-25
ジョン・ディクスン・カー「曲がった蝶番」
若い頃、アメリカに渡る際に沈没したタイタニック号に乗り合わせた過去のあるファーンリー家の次男ジョンは、今ではケント州にある屋敷の当主に落ち着いていた。だが、我こそは本物のジョン・ファーンリーだと主張し、その証拠もあるという男が現れる。弁護士立会いの下、二人のジョンがまさに決着を付けんとするときに怪事件が。
ここ最近、創元が力を入れているカー新訳、1938年だからこれも作者に脂の乗っていた時期の作品ですね。旧『曲った蝶番』は大昔に読んでいるのですが、記憶はあいまい。上に書いたような設定はなんとなく覚えていたけれど。
ミステリとしては衆人環視下の犯罪、いわゆる準密室なのですが、それに加えてどちらのジョンが本物なのか、事件は自殺なのかそれとも他殺なのか、という問題も絡んでなかなかに広がりのあるものになっています。更に悪魔崇拝の儀式や不気味な自動人形による怪奇趣味も充分。
また、プロットもミステリのルーティンを意識しつつ、そこからずらした展開が愉しいし、途中で披露される仮説も手が込んでいてと、とにかく読者を飽きさせないサービスが満載です。
さて、真相なのですが。
終章で明らかにされる強烈なトリックは推理困難なものであり、その異様なテイストは乱歩が好みそう。ただ、全体に色々と手を広げ過ぎたせいか、解決全体として見るとごたごたしている感は否めないところ。細かいひとなら証言の扱いがアンフェアだと思うのでは。
カーの個性が非常に強く出た一作であって、好みは分かれそうですな。完成度は置いといて、個人的には無類に面白かったのですが。
2012-12-24
Gil Scott-Heron / The Revolution Begins
どうしようもなくなって落ち込んだときには
ビリー・ホリディやコルトレーンを聴けばいい
彼らが問題を洗い流してくれるさ
("Lady Day And John Coltrane")
英Aceからギル・スコット・ヘロンのキャリア最初期、フライング・ダッチマン・レーベル在籍時に残した録音を纏めた三枚組CDが出ました。
ギルはこの当時三枚のアルバムを制作しているのだけれど、今回のセットではそれらのシークエンスがばらされているので、そこは好みが分かれるところ。
ブックレットには当時のスタジオ風景の写真が多く載せられ、ライナーノーツは相棒ブライアン・ジャクソンやプロデューサーのボブ・シールのコメントが盛り込まれたもので読み応えがあります。
ディスク1は「SONGS」と題されていて、唄物を集めたもの。ファースト「Small Talk At 125th And Lenox」(1970年)から2曲、セカンド「Pieces Of A Man」(1971年)からは1曲を除いた全部、サード「Free Will」(1972年)から半分。改めて聴いても、都会的で硬派な面とメロウさのバランスが実に格好いい。
今まで敬遠して聴いていなかったファーストにも唄物といっておかしくないトラックがあった、と判ったのが個人的には収穫。しかし、せめて制作時期順に曲を並べて欲しかったというのが本当のところです。
ディスク2は「POETRY, JAZZ & THE BLUES」。内容は三枚のアルバム収録曲のうちディスク1に入れてない曲全て。殆どがポエトリー・リーディングで、箸休めのようにブルースがちょこちょこ混じっています。バックがパーカッションのみのものが多く、内容は社会的テーマが中心で口調も堅めとあって、CD1枚通して聴くのはなかなかキツイものがある。
バーナード・パーディのアルバムに客演したときの曲もひとつ入っているのだけれど、これといって特徴のないブルース。このディスクはあんまり聴かないかも。
ディスク3「THE ALTERNATE FREE WILL」はその名の通り、サードアルバム「Free Will」のオルタネイト集で、「All previously unreleased」と書かれています。ただ、僕は未聴なのだけれど過去に「Free Will」に8曲の別テイクを付けたCDが出ていたそうなので、もしかしたらそれとダブるものもあるかもしれません。
リマスターは文句無し、ナチュラルで長時間聴いていても疲れない。いつもながらAceの仕事は抜かりが無い。
ただし、入門編には向いていないセットではあります。これから初期のギル・スコット・ヘロンを聴こうか、というひとにはやはり単体で「Pieces Of A Man」を勧めます。
2012-12-23
法月綸太郎「犯罪ホロスコープⅡ 三人の女神の問題」
法月版「犯罪カレンダー」、その後編。
収録されている六短編のうち、前半三作にはストレートなフーダニットが並んでいます。キャラクターの扱いが実に淡々としていて、容疑者が伝聞でしか登場しない作品もある。そしてその分、謎解きは濃ゆいものになっています。
「宿命の交わる城で」 次々に意外な仮説が提示される様が作者の初期作品を思わせるようで、とても密度の高い短編。ねじれた犯罪の構図は勿論、小説としての人を食った趣向も洒落てる。
「三人の女神の問題」 非常にパズル的な要素が強い一編。これも錯綜した事件のもつ奥行きが素晴らしい。構図の反転も鮮やかに決まったし、ねちっこい推理も良い。
「オーキュロエの死」 シンプルな構成要素にして複雑なプロットが凄い。星座を絡めた趣向もばっちり決まった。
後半の三作は設定そのものがちょっと変わったものになっています。そもそもメインとなる謎が何なのか、というところから捻っていて。
「錯乱のシランクス」 被害者自身が後から書き足したダイイング・メッセージという妙。これはいかにも後期クイーンらしいな。
「ガニュメデスの骸」 奇妙な誘拐事件は意表をついた展開を見せていく。その先読みさせないプロットが見所。
「引き裂かれ双魚」 異様な論理を扱ったものであるが、ダイイング・メッセージの補助的な使い方が面白い。意図せぬところに暗合を見てしまうところなんか丁寧。
ロジック/プロットいずれに重心をかけた作品であっても、ちゃんと意外性があるところが良いですな。星座の縛りを守りながらバラエティもあって、オーソドックスな探偵小説好きを満足させてくれる短編集です。
2012-12-22
Del Shannon / Home & Away
デル・シャノンの英国レコーディング音源、制作は1967年。プロデューサーとしてはアンドルー・ルーグ・オールダムがクレジットされており、アレンジはアーサー・グリーンスレイド、演奏にはスタジオミュージシャンに加え、イミディエイト・レーベルの人脈が多く参加しているようです。
内容はアンドルーの趣味のウォール・オブ・サウンドに、フォークロックとバロックポップの混交、といった感じ。しかし、英国のスタジオで英国のミュージャンによって作られた音であるにも拘わらず、デル・シャノンのボーカルが乗っかるとアメリカンポップに聞こえる不思議。どういうことだろう? と考えながら何度も繰り返し聴いてしまった。シンガーとしての格なのか、湿り気のない明快な唄声がバックのいかにも英国らしい陰りを帯びたトラックを支配しているよう。
曲によってはサウンドと唄にミスマッチな感を覚えるものもあるのだけれど、結果的にはそのことによってちょっとした掴みどころの無さと独特の奥行きが出ているようでもある。
楽曲はビリー・ニコルズやトゥワイス・アズ・マッチらによるものと、デル・シャノン本人が書いたものが混在しているのだけれど、メランコリックな佳曲が多いですね。
唯一、これは浮いているんじゃないかと思ったのが "Runaway '67"。かつてのヒット曲をテンポを落としゴージャスなオケを使って再演したもので、アンドルーのスペクター・コンプレックスが悪いほうに出たかな。
当時のイミディエイトの音が好きな人なら、聴いて損はない一枚ではないかと。
2012-12-16
レイモンド・チャンドラー「大いなる眠り」
二年ぶりとなる村上春樹訳チャンドラー、その第四弾。我が国では双葉十三郎が訳した東京創元社版で長らく親しまれてきた作品だけれど、この本も「翻訳権独占 早川書房」と腰巻には書かれていて、どうもチャンドラーの作品の版権はすべて早川に移行したようであるね。数年前にこの作品は田口俊樹が訳し直した、それが創元から新たに出る、という話があったそうなのだけれど。
『大いなる眠り』は長編第一作だ。スタイルは既に完成されているのだけれど、後年のものと比較するとフィリップ・マーロウは若々しい。やたらと感傷にひたることもないし、比喩もぶっきらぼうだ。脇筋も控えめ、引き締まった文章はこの作品ならではであって、チャンドラー長編の中では一番ハードボイルド小説らしい。
筋を説明する必要があるだろうか? 特に珍しいところはない、金持ちの依頼人が身内の持ち込んだトラブルに片を付けるために探偵を雇う、いつもそんなお話だ。
チャンドラーが偉大な先達・ハメットから受け継いだことのひとつは、読者に先読みさせない展開だろう。いや実際、なぜこんな風に話が繋がるのだろう、と不思議に思う。
そして、マーロウが情報を売り込まれた後に考える、こんなくだりがある。
「話はいささか整いすぎていた。そこに見受けられるのは複雑に織り込まれた事実の模様ではなく、そぎ落とされたフィクションの単純さだった」
あるいは、その一見した脈絡の無さと、偶然もしくは運命的なタイミングに支配された展開こそが彼にとっての現実らしさなのだろうか。
この作品は十年以上読み返していなかったのだけれど、マーロウが依頼人と温室内で会う場面は良く覚えていたな。
2012-12-09
デュレンマット「失脚/巫女の死」
スイスの劇作家、フリードリヒ・デュレンマットの中短編集。採られている作品はいずれもエンターテイメントとして読めるものばかりであります。300ページちょっとで千円越え、と文庫本にしてはちと値が張るのだけれど。
「トンネル」はオーソドックスな不条理ものですが、まあ、でぶのドタバタ劇です。心理に深く踏み込まず、淡々とした描写によって生み出されるそこはかとないユーモアもいい。軽々しく「ここではないどこか」とか言ってるやつらは皆、この列車に乗ればいいのだ。
「失脚」で描かれているのは独裁政治のグロテスクなカリカチュア。革命をめぐる奇妙な論理が展開するうちに、状況が一転していく。恐怖に支配された喜劇でもあって、笑いながら読みました。
「故障」はミステリの世界でもありそうな設定のものであるけれど、展開が読めるよな、と思っているとあれあれ・・・。チェスタトン的でもあるか。
最後の「巫女の死」は有名なギリシア悲劇を素材にして好き放題遊び倒した一編。死に瀕した巫女の前に「オイディプス王」の登場人物たちの幻が次々にあらわれ、真相は実はこうだったのだ、とそれぞれに違う告白をしていく。繰り返しギャグでもあるし、ミステリのパロディとしても読めるか。
少し理屈っぽいですが、初期の筒井康隆みたいなところもあって気に入りました。結末において物語世界の底が抜けるような感じで、寓意を探ろうとすればいくらでも掘れそうではありますが、まずはただただ面白く読むが吉かと。
2012-12-02
Tami Lynn / Love Is Here And Now You're Gone
タミー・リンというニューオーリンズ出身の女性シンガー、1965年にバート・バーンズ制作で "I'm Gonna Run Away From You" をリリースしていますが当時は話題にならず、その後はセッションシンガーとして活動していたそう。1971年にはジェリー・ウェクスラーから声が掛かり、マイアミのクライテリアスタジオにおいてウェクスラー&ブラッド・シャピロの元でシングルを制作したものの、これもヒットには結びつかなかった。しかし同年、イギリスの所謂ノーザンソウルシーンで前述の "I'm Gonna Run Away From You" に火が付いたそうで。そのイギリスでのリイシューを企画したジョン・アビイというひとが、タミーをマラコスタジオに連れて行って作られたのが、「Love Is Here And Now You're Gone」(1972年)というアルバムです。
アナログA面にあたる前半はメドレーというか組曲風で。収録されている4曲は全てカバーなのだけれど、その間を語りが繋ぐことでひとつのストーリーが構成されているという具合。
頭から3曲は控えめな演奏による、カントリーを隠し味にしたようなしっとりしたスロウなのですが、丁寧で表情の細やかなボーカルがしっかりと嵌っています。中では、タイトルにもなっているスプリームスのヒット曲がメロディはそのままにぐっとテンポを落としたものになっていて。淡々とした演奏を背景にすることで、展開をはらんだメロディが一段と際立っているようで、気に入りました。
そして、スロウがずっと続いた最後にはキャッチーなミディアム "That's Understanding" が来るのだけど、これがそれまでの抑えに抑えた流れからの開放感もあって、ばっちり決まった。
対して、アルバム後半はポップで軽快なダンサーが中心になっていて、あっさりした唄い口は曲調に合っていると言えばそうなんだけど、ソウルのプロパーなファンにはもの足りなく感じられるかも。
ただ、最後にはマイアミ制作のシングル両面が続いていて、それらはタイトで都会的なテイストのサウンド。呼応するようにボーカルも力強く、これには満足。
軽量級ではあるけれど、南部らしい甘さを滲ませた佳品だと思います。やはりロマンティックな前半がしっかりと作られていて良いな。
登録:
投稿 (Atom)